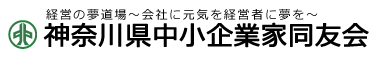有限会社マス・クリエイターズ 代表取締役 中林 正幸氏
写大時代の仲間は宝物
貪欲に最高の写真を撮り続ける

神奈川県中小企業家同友会の広報と言えば、この人、有限会社マス・クリエイターズの中林 正幸氏だ。中林氏が広報委員長を続けられるように、理事は最長4年という神奈川同友会の規約を6年に改訂させるほどの活躍で、2017年から広報委員長を6年務め、2023年4月で勇退する。
ご本人はこのシリーズに載ることを固辞したが、広報委員会の全会一致で感謝をこめて取材させていただいた。
750ライダーに憧れて
アルバイト三昧の少年時代

中林氏は1960年に梵鐘をつくる鋳物職人の父と写真フィルムの現像やカメラ販売を行う写真店を営む母のもとに長野県松本市で生まれた。姉と妹がいる。
中学時代までは背が低く、毎年学年で一二を争っていた。しかし、中学で選んだクラブ活動はバレーボール部。中学1年の時は日本独自の9人制だったが、その後日本が国際ルールに則るようになり、クラブ活動も6人制となる。そうなると背の小さい中林少年には出番がなくなる。仕方なく退部し、いろいろなクラブを転々とするが最終的には帰宅部に落ち着く。
この頃、週刊少年チャンピオン(秋田書房刊)に連載されていた「750(ナナハン)ライダー」に憧れた。高校に入ったら絶対にバイクの免許を取ると心に決め、県立高校に進学する。750ライダーの主人公「早川 光」の名前で作ってもらった電車の定期券は今でも宝物だ。
高校入学直後からバイクを買うために新聞配達を始めた。朝5時に起きて、およそ100軒分の新聞を自転車で配達する。学費もできるだけ自分で賄うつもりだったという。16歳になってすぐに中型自動二輪免許を取得した。すぐに50ccバイクを購入。夢の750には手が届かなかったが、このバイクが非常に役に立った。新聞配達の効率が劇的に変わった。自転車だと2回に分けていた配達でも、機動力のあるバイクなら1回で行ける。電車通学ができるからと言って入った高校だが、バイク通学に切り替えた。長髪で後ろに女の子を乗せて走ったりもしていたそうだ。
バイクの免許を取ったことで年賀状配達のアルバイトもしていた。新聞配達をしていたこともあり、土地勘は普通の高校生よりもはるかにあった。そのため、他の学生よりも多くの数を短時間で配達できる。夏休みも来ないかと、郵便局の集配課の課長から声がかかり、大学生並みの時給をもらっていた。
他にもスキーシーズンの夜間、ドライブインでも働いていた。最初はアメリカンドッグの販売や皿洗いがメインだったが、料理長に見込まれいつしか料理の仕込み担当になっていた。
ここでも手際の良さを買われ、高校生だというのに時給は大学生並みにもらっていたという。
アルバイトが嫌な時もあったが、効率よく、まじめに働いていたためか、学費はもちろん、バイクの維持費や遊ぶお金も稼いでいた。
進路が決まらない!一転、写真の道へ
高校3年になり、周りは就職先や進学先が決まる中、中林氏は進路に迷う。地元での就職は職工職が多く、ピンとくるものがなかった。そうこうしているうちに年も明け、業を煮やしたのか、ある日帰宅すると母と国語の先生がお茶を飲みながら中林氏を待っていた。東京の大学へ推薦で入らないかと話しを持ってきてくれたが、興味のない学部で乗り気になれない。
すると今度は郵便局の集配課長と副局長が「とりあえずアルバイトで入り、公務員試験(当時は郵政省管轄)を受けて正式に職員になってくれ」と言ってきた。公務員自体は魅力だが、雨の中、カッパを着て配達することを考えると、一歩を踏み出す気にはなれなかった。
そんな日々の中、母が「こんな学校もあるけど」と東京工芸大学(旧・東京写真大学)のパンフレットを見せたくれた。母としては現像だけではなく撮影も行う写真館にしたいという気持ちもあったのだろう。小さいころから暗室作業の手伝いをし、小学校の卒業文集には将来はカメラマンになると書いていたのを思い出した。
そこで2月になって高校を通して推薦入試を受けるが、不合格。そこから1か月間、死ぬ気で勉強をして合格。東京工芸大学短期大学部写真技術科に入学した。
またもアルバイト三昧の写大時代
入学直後に仲良くなった3人と何かサークルをやりたいよねと鉄道研究会(以下、鉄研)に入る。バリバリの撮り鉄かと思いきや、鉄道で旅行をすることがメインの楽しいサークルだ。この時に仲良くなった3人とは今も助けあって仕事をしている。運命の下宿4人組だ。
短大なので1年の途中から専攻を決めなくてはならない。母には、実家に戻り写真館をつくると思われていたが、営業写真ではなく商業写真を専攻する。その結果、母から仕送りを止められてしまった。
すると、ある日、鉄研のOBから結婚式場の写真撮影のバイトをしないかと誘われた。結婚式から披露宴までのスナップ写真を撮る仕事だ。スナップ写真を見せて気に入ってもらえればアルバムを作成する。売れれば1冊8000円になる。新郎新婦両家が買ってくれるので、実働2時間で1万6千円が稼げる。売れなければ交通費の2千円だけになる。いかに良い写真が撮れるかにかかっている。
勉強熱心な中林氏は撮影ポイントを着実に覚え、喜んでもらえる写真のコツをつかんでいった。いつしか1ヶ所お試しだった結婚式場のアルバイトは都内の有名式場数か所になった。
気が付けば短大時代もアルバイト三昧。卒業制作さえ忘れる毎日だったが、優秀な成績で卒業した。

写真事務所に就職!
しかし24歳で退職し、フリーランスに

当時の初任給は短大で約10万円。その頃すでに中林氏はアルバイトながら月に8万円稼いでいた。アルバイトの一つに先輩の紹介でカメラマンのアシスタントもあった。そのカメラマンが独立して法人化すると、事務所に誘われた。給料は相場よりも安かったが、就職活動をしていなかったこともあり、二つ返事で「お願いします!」と入社を決めた。写大2年の秋のことだ。
ところがそのカメラマンが急逝してしまう。事務所はカメラマンの妻が引継ぐことになり、就職先はなくならずに済んだ。
事務所での初仕事は、卒業式で飲んだくれ、二日酔いのまま向かった電電公社の社内報の仕事だった。 酒臭いまま、ガムを噛み続け、必死に酔い覚ましをしながら向かった。印刷された社内報を見て、自分が撮り、自分の名前が載った写真を見た。うれしかった。
しかしそれ以降、なかなか簡単には撮らせてもらえない。そのうちに事務所が現像などの暗室作業を請け負うようになる。明けても暮れてもアシスタントと暗室作業ばかり。くさりきって、暗室作業だけなら撮らない!と宣言した。
そこに天から助けがやってくる。中林氏のカメラマン人生を決定づけた大日本印刷の佐藤氏だ。佐藤氏自身も凄腕のカメラマンだった。佐藤氏は中林氏を可愛がり、何かとアシスタントに呼んでくれた。撮影技術を叩きこんでくれたのも佐藤氏だ。中林氏の生来の真面目さもあり、貪欲に技術を盗み、自分で同じ条件や構図を作成して写真を撮って復習する。みるみる腕を上げていった。
ちょうどその頃、中林氏は当時流行っていたグルメ雑誌の撮影の仕事を得る。取材に行き、料理と店内を撮影する。そのグルメ雑誌の編集者と数年後に結婚した。
しかし、事務所内の確執に巻き込まれ、中林氏には撮影の仕事が回ってこなくなる。独立しようにも「中林には仕事を回すな」と事務所があちこちに連絡して回っていた。その上、佐藤氏も名古屋に転勤が決まってしまう。「独立して俺がかえってくるまで2年間、何とか耐えろ」と佐藤氏に言われ、事務所を退職。若干24歳でフリーランスのカメラマンになった。
悔しさをバネに料理カメラマンに

コニャックにて
なんとか独立したのは良いが、良いカメラ機材がない。車のローンも払えない。
そんな中林氏の救世主はグルメ雑誌の出版社だった。国内に輸入されているワインとナチュラルチーズの事典を作る仕事のカメラマンに、事務所に内緒で中林氏を起用してくれた。商品点数の多さにへとへとになりながらも、8,000点のワインと2,500点のチーズを収めた事典を編纂した。
少しずつ料理業界での写真の仕事が増え、ホテルやレストランの撮影の仕事が増えた。時はまさにバブル絶頂期。フランス料理の撮影の仕事は引く手あまただった。
撮影用の料理は、下げられるとカメラマンもお相伴にあずかることができた。しかし、ある日、有名シェフから「カメラマンなんて味もわからないんだから、食わせることはない」と言われ、カメラマン魂に火が付いた。
当たり前なのかもしれないが、フランス料理を作る時に「それ、ポッシェして」などとフランス語で指示される。フランス語に触れたこともない中林氏にはわかるはずもない。帰り道にフランス料理用語辞典を買い込み、耳で聞いた単語をひたすら調べた。
そうしてフランス料理用語を勉強し、撮影を重ねるうちに、より美味しく見える調理加減やサーブ方法を提案できるようになってきた。バブル経済はまだ続いていた。中林氏には一流ホテルからの撮影依頼が引きも切らなかった。
そして、1988年に有限会社マス・クリエイターズを設立した。
人生最高の1枚

「ホテル・クリヨンから見る
エッフェル塔」

一緒に厨房でランチ
料理カメラマンとして名をあげ、フランス料理に強かった中林氏はフランスへ渡航しての仕事も増えた。フランス語は話せないが、何を言っているのかはわかるそうだ。
1991年1月、憧れのホテル クリヨンの撮影の仕事を得て、フランスに渡航した。ホテル クリヨンと言えば、故ダイアナ妃が最後に宿泊していた高級ホテルとして有名である。
クリヨンの前にロワール地方の古城を撮影するという企画だった。忘れもしない1991年1月17日、ロワールからパリのホテルに帰ると、ホテルが封鎖されていた。湾岸戦争の多国籍軍にフランスが参戦し、パリは爆弾テロが多発していた。日本からはすぐに戻ってこいとテレックスが届いていた。
しかし、ホテル クリヨンを撮るまでは日本に帰らないと一度は断った。その後、同行していたライターと話し合い、空港まで行ってみたもののすでに航空券は売り切れ、本当に帰国できなくなった。こうなったらもう飲むしかないとライターと飲んだくれていたら午前2時に電話が鳴った。事情がよくわからないが、とにかく30分後に迎えに行くから、荷物を持って降りてこいという。慌ててGパンを履いて降りていくと、そこにはベンツのリムジンが迎えに来ていた。
仕事の依頼主がそんなに情熱を持って撮影したいと言うなら、クリヨンに来てもらおうと計らってくれたのだ。しかし、高級ホテルであるクリヨンに厳戒下に普通に入っていくことはできない。重要人物に見せかける必要があると用意されたのがベンツのリムジンだった。クリヨンの周囲は警察車両と装甲車に囲まれていたが、2日間好きなようにどこを撮影しても良いという許可がおりた。
カメラマンとしての最高の1枚はどれかと聞かれたら、この写真と答えるだろうと言って1枚の写真を見せてくれた。ホテル クリヨンから少し遠くに見る、美しい三日月のかかったエッフェル塔の写真だった。
バブル崩壊と写真のデジタル化の始まり
運命の下宿4人組、ふたたび

湾岸戦争が始まった頃、バブル経済が崩壊する。商業写真も最初の頃はさほど影響を受けなかったが、1994年ごろから徐々に影響を受ける。1男2女を授かっていた中林氏だったが、仕事は減る一方だった。
このままではつぶれてしまうと、写真館を作ることを決意する。背中を押したのはもちろん奥様だ。そして、写真館のノウハウを教えてくれたのは写大時代の「運命の下宿4人組」の一人だった。老舗写真館を営む友人とその父の助けもあり、1996年12月に「スタジオ ラ・フェット」を開業する。
当初、成人式や七五三といった記念撮影を想定していたが、いきなり証明写真撮影の依頼がどんどん入ってきた。しかし、中林氏は唯一証明写真が撮れなかった。正確に言えば、フィルム写真での修整が得意でないため、証明写真を撮りたくなかったのだ。食べていくためには証明写真を撮るしかない。そこでフィルム修整ができないなら、修整のいらない写真を撮れば良いと、商業写真で培ったライティングを駆使した証明写真を撮るようになった。
スタジオの裏にあった小学校が横浜市内屈指の中学受験校だったことが功を奏した。いつしか中林氏のスタジオで撮影すると合格すると言う神話ができていた。
だが、良い時はそう長くは続かない。2000年頃からデジタルカメラが市場に出てきたからだ。覚えている方も多いと思うが、初期のデジタルカメラは画質がさほど良くなかった。しかし、徐々に画質があがってくると、フィルムと違い、撮影の場ですぐに画像確認ができ、フィルムや現像の経費が掛からないことから、あっという間に普及していった。
スタジオでの現像とプリントの収入はみるみるうちに減っていく。そこにリーマンショックが追い打ちをかけ、スマホが出現する。デジタルカメラのように使える電話には太刀打ちできない。売り上げは2000年と比較して50%減になっていた。
設備投資が重くのしかかり、廃業も考えるようになった時、スタジオ開設当時から働いてくれているパート社員が、「ここでつぶれてはいけない」と助け船を出してくれた。
涙が出るほどうれしい厚意を無駄にするわけにはいかないと、運命の下宿4人組に相談した。仲間の一人が提案してくれた動画撮影に活路を見出した。
東京だったら、ここに行けば機材はすべて揃うと教えてくれた。銀行からもタイミングよく融資が通った。勢いで機材はそろえた。しかし、使い方がわからない。
ちょうど高校を卒業した次女と、機材すべてを車に乗せ、すでに動画撮影をしていた青森にある友人の写真館まで、撮影方法、ライティング、編集方法、修整方法まで一通りのことを教わりに行った。
今では演奏会や会社案内など、動画撮影にも忙しい。
創業24年目で同友会へ入会、広報委員長へ

廃業危機を乗り越えた2012年、カメラマンを探している人がいると、昔スタジオでアルバイトをしていた人が連絡をくれた。その仕事で出会ったのが神奈川県中小企業家同友会の会員だった。2012年に入会したが、当時奥様が足首を骨折していたこともあり、入会したものの幽霊会員だった。
もう辞めようと考えていたところへ、広報委員会へ誘いを受けた。それからはみなさんが知っての通りだ。
2017年に広報委員長に就任すると、神奈川県中小企業家同友会の機関紙「DOYU Kanagawa」の紙面全体を刷新した。積極的に会員企業の取材に向かい、表紙写真を撮る。委員長として6年間、機関紙の企画・編集に携わった。
手に取られることもなく捨てられていることが多かった機関紙が、面白いと言われるようになった。他県の同友会からの評価も高い。間違いなく中林氏の尽力があったからだ。
これからのことを聞くと、地域に根付いたスタジオをそっくり受け取ってくれる方に承継したいという。取材の際にいつも奥様に対する感謝を口にする中林氏。広報委員長退任後は少しゆっくりと、奥様とフランス旅行に行って欲しいものだと思う。
企業情報
有限会社マス・クリエイターズ
本社所在地:横浜市泉区緑園5-29-6-2F フォトスタジオ ラ・フェット内
TEL:045-814-2147
URL:https://mass-creators.jp
<取材・文・撮影/株式会社アールジャパン 荒岩 理津子>