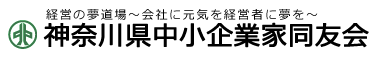野菜づくりに学ぶ人材育成の本質
県央ブログ担当のライフ&キャリアの小川です。
仕事は、組織開発や自律型人材の育成サポート、経営者コーチングを行っています。
仕事の合間に座間市のJAから畑(約60㎡)を借りて、年間を通して20種類前後の野菜づくりをしています。
人材育成の仕事に携わる私にとって、畑で土をいじる時間、農作業の時間は、ただの趣味ではありません。
土に触れ、野菜づくりに向き合う中で、「人を育てる」ことについて考える貴重な時間となっています。

畑から見えてきた育てるということ
「野菜づくり」と「人材育成」。一見別の世界に思えるこのふたつには、実は共通点も多いと感じているので、今回、ブログ記事にまとめてみました。
1. 種を選ぶ—適材適所の始まり
野菜を育てるとき、最初にするのは「種選び」。季節はどうか、気候は合っているか。
原産地はどこか。そんなことを考えながら、自分の畑に合う種を選びます。
人材育成も似ています。まずはその人がどんな環境で力を発揮できるのかを見極めることが、育成のスタート地点。向き不向きを見抜く目と、個性に合った場所を用意する配慮が求められます。
2. 土を耕す—信頼関係という土壌
よい野菜は、よい土からしか育ちません。土を柔らかくし、肥料を入れ、水はけを良くする——このプロセスは、人を育てるための「信頼関係づくり」とよく似ています。
人も、安心できる土壌(心理的安全性)があるからこそ、自分から伸びていこうとするもの。土を整えるように、日々のコミュニケーションや環境づくりが欠かせません。
3. 観察と対話—声なき声に耳をすます
野菜は言葉を話さないけれど、葉の色、形、育ち方でたくさんのことを語りかけてきます。
人もまた、表情や態度、ちょっとした変化にサインを出しています。それに気づくには、日頃からよく「見ている」ことが大事。相手の中にある小さな変化を見逃さず、必要なときにそっと手を差し伸べる——それが育てるということだと思うのです。
4. 待つ勇気と手をかけるタイミング
野菜の成長スピードはそれぞれ違います。早く育ってぐんぐん伸びるものもあれば、ゆっくりじっくり根を張るものもある。
人も同じ。焦って結果を求めすぎると、まだ準備ができていない芽を傷つけてしまうことがあります。でも、ただ放っておけばいいわけではありません。水をやる、追肥をする。その人に合ったサポートを、必要なタイミングで差し出すことが大切です。
5. 実りを喜びまた種を蒔く
収穫の喜びは、育てた人だけが味わえる特別なご褒美。でも、そこで終わりではありません。野菜づくりは次のサイクルへと続いていきます。
人材育成も同じ。育った人が、また次の誰かを育てていく。その循環が生まれてこそ、組織は持続的に成長していくのだと思います。
野菜は手をかけた分だけ、ちゃんと応えてくれます。そして、人もまた、誠実に関わることで確実に育っていく存在です。

以上が私の思う、「野菜づくり」と「人材育成」の共通点です。
これからも野菜をつくりながら、「育てることの本質」を考え続けていきたいと思います。
〈文責 ライフ&キャリア 小川真央〉